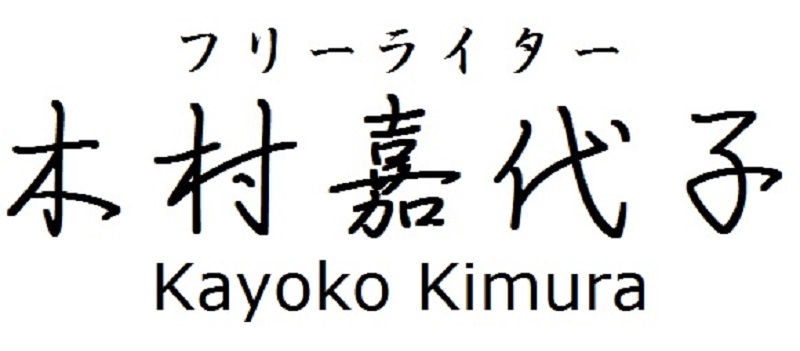フランスの雑誌Altermondeの「科学と民主主義」特別号に掲載された、「民主主義の核」の記事の抄訳です。
この記事は、福島第一原発事故の前に準備していたそうです。
福島第一原発事故そのものと、この事故による健康および環境への計り知れない影響は、チェルノブイリ事故から25年たっても何も変わっていないことを示している。原子力は産業として存在しているが、そのリスクは実際に誰もコントロールできない。軍事産業がそれを出現させ、その闇の習性に定められた原子力業界では、人々の意見がほとんど反響を呼ぶことはない。
いたるところで行われている原子力研究は、歴史的に、軍事的な関心に向けられる。「この技術を所有するのは、“大国の取り巻き”に加わることであり、地政学のチェス盤に影響されるている」とCERES(環境・社会情報研究センター)のスザン・トプシュは強調する。「産業と文明への原子力計画がはじまったのは、経済発展に伴う莫大なエネルギー需要に応えるためであり、60年代の中ごろにすぎない。1973年の石油ショックがこの傾向を決定づけ、先進国を石油の代替物の探求へと導いた。フランス、というよりフランス政府は、全面的に原子力を選択した」
予測不可能な危険、解決できない放射性廃棄物の問題、さらには、その技術が消費社会と警察社会を作り上げる手段であることを指摘し、反対運動はそのとき生まれた。しかし、こうした議論が原発の出現を可能にしてしまった。「原発選択の正当化に関する疑問は、フランス人に問われることは一度もなかった」と、CRIIRAD理事長のロランド・デスボルドは認識する。「議員たちは、1991年にバタイユ法(放射性廃棄物管理研究法)の制定で、放射性廃棄物の行く末を解決しなければならなかった。2006年のもうひとつの協議では、TSN法(原子力に関する透明性および安全性に関する法律)にいたった。しかし、議論はいつも周縁を対象にし、根本的な問題を提起しなかった。1986年のチェルノブイリ事故で、ヨーロッパ諸国の政府は原発問題の政策を転換した。それに最もかけ離れていたのがフランスだった。世論の情報を歪曲し、高気圧が国境を超える雲を防ぐと天気予報で証明し、それを信じ込まされた」とスザン・トプシュは述懐する。その反動で、反原発団体はその後、情報の透明性の問題に集中しがちだった。「極端な秘密政策を行使する一方で、フランス政府は、情報へのアクセスという点だけを問題にした異論の“操作”に躍起になった」 仕方がないので、人々はせめてもと過ぎ去った沈黙と嘘の時代を考えていた。しかし、福島第一原発事故により、全然違うことが起こった。
事故の直後から、鉛のような天井が原発施設の崩壊した原子炉の上に倒れ、放射線を抑制する代わりに、情報がブロックされた。危険に身をささげた作業員は、制御不能になった原発施設と格闘している一方で、日本政府は国民に安心させようとしていた。汚染レベルは人の健康には影響ないが、汚染された地元農産物を購入したり、東京の水道水を飲むことを控えるよう指示するという、矛盾した発表が続いた。実際のところ、損害の実際の大きさがわかるのには、数ヶ月後、たぶん数年後かかるに違いない。
地震地帯であり、さらに核の危険に敏感である国に原発を建設するにあたり、日本は効果的な原発施設防護について理解していなかったのか。他の国、特に南の国々(発展途上の国々)の状況を考え、事故に直面して明確な行動がとれなかったのか。ニジェールのようにウランの生産地は沈黙に支配されている。グリーンピースとCRIIRADは、ニジェールの探鉱地帯の地下水層の汚染を確認し、すべての公式報告書を否定した。サハラ砂漠や(フランス領ポリネシア島の)ムルロア環礁での核実験の影響をめぐる沈黙もまた、地元住民、もしくはフランスの現地職員、軍隊やそれに準ずるものにとって同様である。アメリカを比較としてあげれば、米軍兵士の被ばくが確認され、10年前から補償対策がとられている。

ヨーロッパのいくつかの国では、福島第一原発事故が非常に大きなショック効果を与えた。スイスは原発の新規建設の認可をすべて保留し、ドイツは自国の原子炉の運転期間延長に猶予を与えると発表した。しかし、フランスでは、エネルギーの選択について話題にするのは、明らかにタブーのままだ。「現在、フランスの電気の78%は原子力エネルギーだ。政府は40年前からこの方針で、どの政党が政権をとっても意見を曲げない」とグリーンピース・フランスのソフィア・マジノニは強調する。「我々は、ヨーロッパの再処理燃料を担っている中心的存在で、隣国の放射性廃棄物を回収する際は、周辺住民の声に耳も貸さずにその国を横切って放射性物質を輸送している。それに加えて、京都議定書では原子力が気候温暖化問題の解決策として紹介された。フランスはこうした方針に従っているだけでなく、損をしてまでも原子炉を外国に売ろうとしている」 多くの新興国が、エネルギーの理由だけでなく、原子力技術を効果的に手に入れようとしている。「ブラジルでは、水力発電で需要の70%以上をカバーしている。原子力は戦略地政学の問題だ」とソフィア・マジノニは続ける。「原子炉の冷却する水がない地域に原発施設は適していないにもかかわらず、アラブの多くの国で同じ試みが見られる。フランスは原子炉をあらゆる国に売りつけるようとしており、そこには政治情勢が不穏な国も含まれている。ニコラ・サルコジがリビアとの契約を計画していたときがあったことを覚えているだろう」 日本の大惨事は、こうした傾向を転換するのに十分ではないか? なのに、何もはっきりしていない。
こうした核のセールス外交の姿勢は、まったくもってフランス独特である。「フランス政府は、フランス電力公社やフランス原子力庁をはじめ、業界すべての有力な株主だ」とロランド・デスボルドは説明する。「そこで問題になるのは、企業が従うべき規制を作っているのも国であり、企業がそれを遵守しなければならないことにある」 原子力業界の経営陣と責任者すべてが、国立高等工業学校(Ecole des Mine)の同窓生で組織されおり、内輪になりがちである事実も加わり、閉鎖の可能性はほとんどないという状況にいたるのは容易だ。
決定機関が原発推進を選択するのであれば、民主的な議論はどこに残されているのだろう? フランスでは、原発施設立地地域の地元住民への情報提供のために、地域情報委員会(CLI)が設置されている。しかし、実際にはそれにどれほどの力があるだろうか? 住民が入手できる資料は、原発運営業者の責任だけに支配されている。公開する情報を選ぶのは運営業者だ。新規建設計画は、調査の過程を通し、公開協議にかけられる。公開討論国家委員会が開催して議論が行われるが、そこでの選択肢は、原発施設以外なにもない!
「他の国では、人々の議論の場がより多く設定されており、ものごとが動く」とロランド・デスボルドは言う。「アメリカでは、1979年のスリー・マイルス島の事故以来、新規の原子炉は建設されていない」 それでは、自由な議論をするには、フランス国内で似たような大事故が起きるのを待たなければならないのか? 今日、1977年に運転を開始し、地震地帯に位置しているアルザス地方のフッセンエイム原発への懸念が集中している。しかし、今のところ、監視査察だけが通知された。議論をまとめたがっているニコラ・サルコジ曰く。「我々はロウソクの時代に戻ることはないだろう」