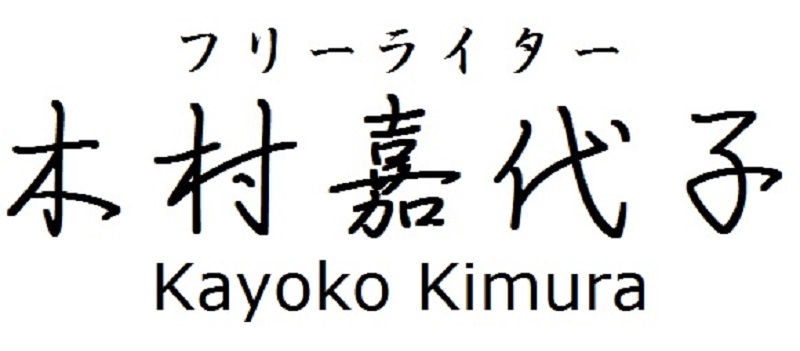2011年6月、福島で4人の女性(母親)からお話していただきました。

そのなかで出てきたのが、行政や学校にかけあう際にぶつかる壁。
これは、福島の原発事故に限ったことではなく、これまで打破できなかったがために、今回、子どもを巻き添えにした大きな犠牲へとつながったと感じます。
以下は女性たちの会話です。
Aさん:遺伝子組み換えや狂牛病など、問題が起きるじゃないですか。そういうのにいつも反対してきましたけど、反対しても止まらないんですよね。全部男の人たちが決めるから。
Bさん:そうなんですよ。
Aさん:おじさんたちが決めるんだ~、と。私が子どもに食べさせたくないのに、「ご飯を作らないおじさんたちが決めるの?」と。おじさんたちはわからないみたいです。
Cさん:子どもの教育の場が良くならないのは、教育を考えている人たちが、頭にちょんまげつけている人ばかりじゃないかって。文科省もそうですし。変わることをいやがる人ばかり。前例がない、と言うのですが、その前例って誰が作ったの? 審議会のメンバーも、どこかの教授とか、コメンテーターとか名のある方であっても、「はたしてこの人たちってのは、現代進行形?」と疑ってしまいます。「実際に中学生や高校生を持ち、悩んで考えている人たちなんですか?」って。そういう人が入ってなかったりするんじゃないですか。文科省は、いつまでたっても、江戸時代や明治時代のままじゃないかと思うんです。
Cさん:確かに自分たちも原発事故や放射能について、きちんと知らなかったのですが、4月ぐらいになると、放射能に関してもわかってきて、そのとき、「何か違うな」と思ったのは、福島では大人も子どもも一緒に被ばくしているわけじゃないですか。なのに、「被ばくをどうして心配してくれないの? これって何だろう」って。「地産地消でがんばろう」と言うけど、「え? そうなのね」と。結局、県民の命はそっちのけにして、経済、経済という。「あー、そうなんだ」みたいな。子どもがいなくなったら、もう未来がなくなってもいいんですか?
Aさん:何か感覚がずれてますよね。
Bさん:結局、行政の職員は4年で移動があるので、その間、何もなければいいんですよ。
ーさもしいですね。
みんな:同類ばかり。サタンですよ。
Bさん:政治家でさえ、あれほど勉強して、あれよ。なんで? 何のために勉強するかといったら、世の中をよくするため。それを小さいときから教えておけば、こんな大人にならないですよ。
Cさん:日本人は「人に迷惑をかけないように生きよう」と教えられますが、それだけじゃなくて、何か大事なことがあるとしたら、「将来はあなたたちの社会なのよ」というか、そういう観点が抜けています。先生がいい例かな、と思うんですよ。私たちの頃は、成績が良かったから、福島大学に進学して、先生になる人が多かったんですよね。なんとなく、そういうふうに先生になった人は、できない人の気持ちとか、自分が経験してないからわからないという人が多くて。みんながみんなそういうわけではないですけどね。苦労して先生になった人もいるし、一概には言えないんだけど。すごくいい素質を持っていても、教員採用に引っかからないかもしれない。校長先生から見れば、扱い人、ということもあるかもしれないので。
Cさん:国会には男尊女卑があるというか。人間として、国政にかかわる資格がない、と思う人もいます。
Bさん:もう見てられないもの、あのケンカやってるの。
Cさん:子どもに見せられないですね。
(2013年9月22日)