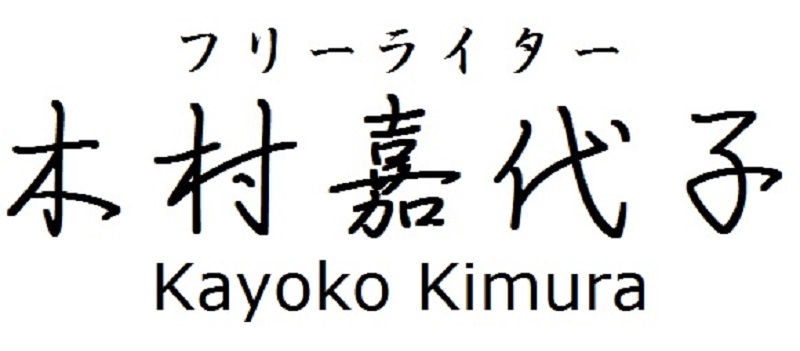フランス版『エル』の2011年12月23日号に掲載されたAlissa Descotes-Tさんのレポートを、個人的に訳しました。名前はイニシャルに変えています。
危険にさらされた子どもたち
フクシマの母親たちの怒り
避難すべきか、残るべきか? 子どもたちを空気のいい地域に移動させるか、家のなかに閉じ込めておくか? 政府が危険性を軽視した状況、そして被ばくの恐怖のなかで、福島の女性たちは絶望に打ちひしがれながらも、救済の道を模索している。
太陽が降り注ぐ道を、3人の女の子が楽しそうにおしゃべりしながら、下校してきた。マスクはしていないが、首に線量計をかけている。「調査するからって、今月末これをもらいました」とひとりが語った。「何て言うんだっけ?」と二人目が質問する。「放射線」ともうひとりの子が答えた。福島第一原発から60キロの福島市で、政府(県)は子どもたちに線量計を配布し、学校の土の除染作業をはじめた。
しかし、日に日に不安を募らせている母親たちにとっては、測定だけで十分とはいえはない。原発事故から9ヶ月、母親たちは、汚染されたなかでの子どもたちを守る日常の闘いについて語った。“避難”という唯一可能な解決策を納得させようとして、周囲の人たちと対立し、彼女たちはしばしば孤立感を深めている。
「子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」の事務所で、Mさんは家賃無料の住宅情報を整理していた。このネットワークは、長期間の「自主避難」希望者の支援で重要な役割を果たしている。「県は避難を勧めていないばかりか、それに反対している」とこの若いボランティアの女性は言う。
ネットワークのサイトにには、避難の説得で悲嘆にくれた母親から、読むのがたいへんなほど多くの書き込みがある。「市役所の人は電話に出るが、答えてくれない。親の不満を聞くだけ。こうした状況は耐えられない」とある母親は書いている。
多くの国際機関や民間団体が公式発表の放射線量測定値を疑問視して以来、母親たちは警戒を強めている。放射線量の年間許容量は、事故後すでに増加している。もうひとりのボランティアのSさんはこう主張する。
「1ミリシーベルトから20ミリシーベルトに変更されたとき、私たちは抗議しました。この数値は原子力施設で働く従業員の被ばく量であることは、誰もが知っています。私たちはモルモットではありません! ある日、若い母親は、学校が子どもたちに線量計を配布したと喜んでいました。親たちは、それが子どもたちを守ると思っていますが、線量計は警戒体制を抑えるだけでしかありません。1、2ヵ月後には、測量計を県に返し、放射能の影響を調べるのです」
約36万人の子どもたちと妊婦に配布された機器は、広島と長崎の被ばくで実施されたテストを連想させる。2つの原爆の投下後にABCC(原爆傷害調査委員会)により実施された経験は、治療ではなく、原子力産業の知識を高めるものだった。「ABCCは現在も広島に存在しています。信じられないかもしれませんが、同じことが福島でも行われているのです」とSさんは言う。
女の子の線量計は、9月に1.7ミリシーベルトを記録した。この結果を発表したにもかかわらず、自治体は「健康には影響ない」と宣言した。
「子どもを守るふりをした計画はこれからも続くでしょうが、今後も政府が問題ないと言うだろうことはわかっています」とSさんはいらだつ。多くの市民団体がネットワーク化されて以来、福島での情報の流れは向上した。しかし、Sさんによると、やるべき手段は残されている。
「ここでの問題は、大半の人が知りたがらないことにあります。母親たちは、匿名を使い、ネットで絶望的な訴えを投げかけています。父親たちは、仕事を辞めたくありません。圧力が非常に強く、子どもでさえ、心配を学校で口にすれば、他の子どもにいじめられます」
ショッピングセンターのアーケードで、Kさんは子どものボディカウンターの測定が終了するのを待っていた。市民放射能測定所に設置されたこの器械は、体内被ばくを測定できる。「子どもは5歳と8歳です」とこの若い母親は説明する。3月12日に原子炉が爆発したとき、彼女は福島市にいた。
「3月18日に家族で北海道に避難しましたが、4月に戻ってきました。子どもたちは、“放射能”という言葉に関するすべてに、ひどくトラウマを持っています。たぶんもう遅すぎるのでしょうが、とにかく知りたいのです」
心配はしているが、彼女は福島にとどまりたいと思っている。「私の両親が実家に戻ってほしいと言っています。でも、ものごとはそう単純にはいきません…」とKさんは笑う。彼女は苗字を明かすのを拒んだ。測定の結果は1ヵ月後にわかる。待ち時間は長いが、福島にはこの一台だけで、この上もなく貴重だ。
「放射能の目に見えない危険を数値化することで、家族の助けになるでしょう。でも、根本的な心配は、食品の汚染です」と市民放射能測定所の所長は言う。この測定所は、5月に福島市に設立された。状況は戦争状態に似ている。
「ここには、心配するのを否定する人もいます。外に洗濯物を干したり、福島の農産物を買いつづけるのは、否定のしるしです。なにはともあれ子どもを避難させるべきだと納得しました」
しかし、政府の「がんばろう福島」キャンペーン以来、「子どものことは心配しないで」がスローガンだ。
「学校は先週、児童を1日1時間だけ外で遊ばせることを決めました」と言うKさんのような親たちを、安心させるにはほど遠い政策。中・高校生の避難問題は、さらに微妙だ。
Nさんは毎日、16歳の長女と確認する。「3月、娘たちと長野県に避難しました。でも、4月9日に長女の高校の入学式に出席するよう、連絡がきました。学校から電話がかかってくるなど、考えたことがなかったのですが…」 それ以来、Nさんは娘の健康を心配している。「末の娘は避難させました。でも、長女は転校したくないと言います。力ずくでそうすべきでしょうか?」
もうひとりの母親Tさんは、息子とぶつかる。「東京近郊で受け入れてくれる家に息子を避難させようと奔走しましたが、息子はそれに反対しました。夫も反対でした」と涙ながらに彼女は言う。二人の女性もまたネットワークのメンバーであり、母親たちに避難を促す証言を受け入れている。しかし、彼女たちの子どもは、一緒に行きたがらない。「同級生と同じでいたいのです。いじめられたり、友達と離れるのが怖いのです。唯一の方法は、子ども全員を避難させることです」と彼女たちは説明する。
子どもと夫が危険性を軽視するという家庭背景のなか、母親は罪の意識と無力さを同時に感じている。
Nさんの長女は、結婚もしないし子どもも生まない、と宣言した。Tさんの息子は、弓道の部活を続けるために残りたがっている。学校の責任者がチェックされる超現実的な状況。
「転校を申し出たら、長女が通う高校は、生徒の了解が必要だと言いました。まったく理解できません」とNさんは驚く。彼女の娘は毎日外で部活を行う。それが母親の心配を増長させる。「ガンや遺伝子異常の可能性があるとさんざん話したので、娘はセシウムを調べる尿検査をしたいと言いました。でも、保健所からは、そうした検査は行っていない、と返答がありました。誰も子どもの味方になってくれないのでしょうか?」
Yさんは、8ヶ月の赤ちゃんに母乳を与えている。彼女は、福島市のホットスポット渡利に4人の子どもと住んでいる。この地域のある地区は、3ヶ月前から4倍の放射線量を記録している。「雨が降るたびに、山から放射性物質が投降します」とYさんは認める。彼女は、「渡利の子どもたちを守る会」のメンバーだ。「私たちは、汚染された場所をはっきり示す地図を作成しました。でも、政府は避難させません」
Y家は、2年前にローンで購入した木造の美しい家に住んでいるが、もうすぐこの家を放棄しなければならない。「新潟県への引っ越しを、夫と決めました」とYさんは言う。「避難は辛い決心でした。この町も、この家も好きです。夫は仕事を辞めなければなりません」 横の居間から子どもたちの大きな笑い声が聞こえる。子どもたちは、プレイステーションの前でくっついて座っていた。
「夏の間、子どもたちは家のなかに閉じこもっていました。それが避難しようと決めた理由です」 Mさんのケースも似ている。彼女は、原発から北東に65キロの郡山に住んでいた。ここは、放射性投降物で非常に汚染されている地域だ。「16歳の息子を受け入れてくれる北海道の家を見つけました。友達と別れるのは悲しいでしょうが、もはやここには戻って来たくはないと思います」と笑いながら彼女は言う。
この母親は、米やコーヒー、その他の北海道の農産物を持って帰り、郡山でミネラルウォーターを無料で供給している。「夫はトラックの運転手で、ローン払いの自宅もありません。それが幸いです!」 たったひとつの心残りは、10年間営業していた飲み屋だ。しかし、これもまた、彼女は放棄する準備をしている。「郡山で最も驚かされるのは、人々が家を再び買いはじめていることです」 地震の後、被災者向けに仮設住宅が建てられた。
「賠償金の使い道として、アパートを借りるより、ローンで家を購入するほうを好むのです。でも、こうしたローンが原因で、多くの家族が避難できないでいます」と彼女は指摘する。福島県は自主避難への資金援助を一切しない。しかし、市民団体のサイトには、公共住宅や受け入れ住居の多くの申し出があり、他県からの連帯を証明している。多くの母親たちが選択した宥和策だ。
田舎のなかの幼稚園で、Hさんは、十数人の子どもを朝早くから受け入れている。この先生は、子どもたちに「思い切り呼吸してもらう」ために、福島市と山形県米沢市を毎日バスで往復することを選んだ。「米沢市は100キロしか離れていませんが、山が自然の壁を作っています」とHさんは説明する。原発事故後、3500人がこの町に避難してきた。
「距離の短さから、母親たちは、避難を待つ間、幼稚園に子どもたちを預けてもいいと思うのです。でも、9月から、米沢市に移住する子どもたちが次第に増えました」とHさんは続ける。新たな移住者のなかで、Mさんは、5歳の娘と10月初旬にここにやって来た。「夫は17歳の娘と福島市に残っています。別居ですが、私は自分の選択に後悔していません。私は雇用促進住宅に住んでいます。2年間家賃は無料です。すでに将来について考えはじめています。少なくとも、娘は安全です」
「広島と長崎で起こきたことを考えると、うまくかないだろうと思います」と、二人の子どもを持つIさんは警告する。「福島では、みんなが思っていることです」。7月から米沢に暮らすIさんは、福島県放射線健康リスク管理アドバイザーの山下氏が、多くのチラシを使って、健康には何の心配もないと宣言したことを思い出す。この情報は瞬く間に広がった。「私もまた、それを信じたかったです」とIさんは説明する。「でも、面と向かって現実を見せようとする、市民放射能測定所の岩田さんのような人たちに出会いました。子どもたちと避難するという選択は、知人たちから批判されました。でも、彼らもいつか、そうする日が来るでしょう」
太陽が米沢の山をゆっくりと昇っていく。毎日の散歩の時間だ。Hさんは、子どもたちをとともに、川のほうへ向かう。何人かの母親も同行している。3つの災害から9ヶ月、福島は少しずつ忘れられていく。広島と長崎がそうだったように、日本は、重苦しい問題にけりをつけることを選んだ。しかし、余震の繰り返しが、意識を目覚めさせ、抵抗の真のネットワークが整った。北海道から沖縄まで、福島の子どもたちを救うために、母親たちが反乱を起こしている。「数ヶ月の悪夢の後、子どもたちはやっと呼吸することができました」と、トンボと遊ぶ子どもたちをやさしく見つめながら、Hさんは言う。「でも、戦いは終わっていません。これは始まりにすぎないのです」
(2012年10月22日)