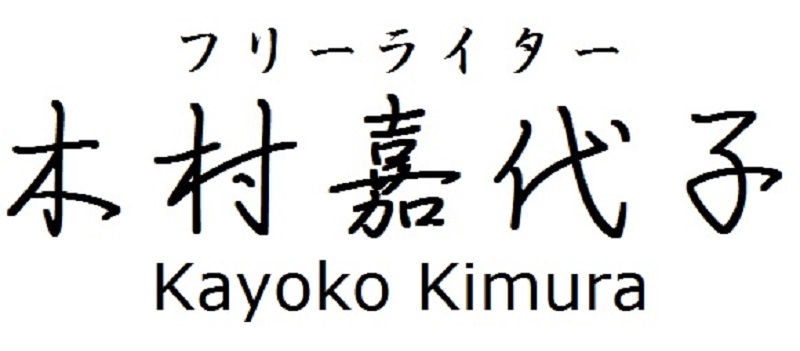『カイ』2010年春号に掲載された記事です。
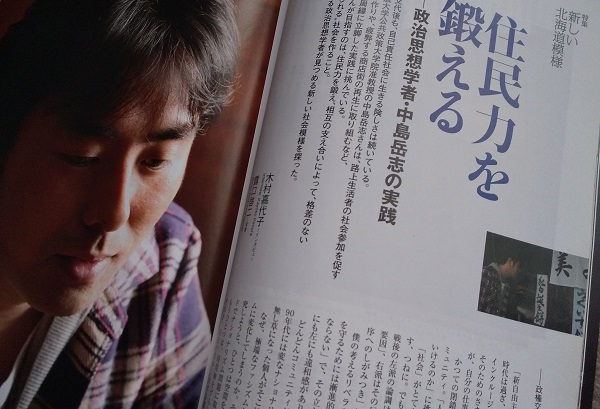
―政権交代をどうご覧になりますか?
「新自由主義をぶっ壊せ!」と声高に叫ぶ時代は過ぎ、これからは、地道にソーシャルインクルージョン(社会的包摂)を浸透させ、そのためのさまざまなケースを作っていくのが、自分の仕事だと思っています。
かつての閉鎖的なコミュニティではないコミュニティ。「人とのかかわりをどう築いていけるのか」に挑戦している段階です。
「社会」がとても重要だと思っているんです、つねに。でも、コミュニティに関して、戦後の左派の論調は「個人の自由を疎外する要因」、右派はその反動で、「固定化された秩序へのしがみつき」にすぎなかった。
僕の考えるリベラルな保守は、「人間関係を守るためには漸進的に変えていかなければならない」で、その立ち位置をとるとき、右にも左にも違和感がありました。
どんどんコミュニティが疲弊化する一方で、90年代には変なナショナリズムが勃興し、根無し草になった個人がそこに飛びついていく。
なぜ、極端なファシズムとかナショナリズムに変化してしまうのか。そのプロセスを研究しようと、ひとつは空間をずらして、インドでナショナリズム問題に取り組みました。もうひとつは、時間軸をずらしたんですね。それが、戦前の日本に対する関心です。
僕が興味を持っているのは現在の日本なのですが。「人が生きれる社会」というんですか。
多様な人間が緩やかにつながりあいながら、承認を得られていく。極端なナショナリズムにむすびつかず、一定のデモクラシーが機能する社会。左右を超えて、そうした社会を築きたいんですね。
保守思想というのは、そんなに間違いではないと思っています。保守リベラルと社会民主主義がしっかり手を結び、新自由主義とリバタリアニズム(自由至上主義)に対抗する仕組みを作らなければならない。
政権が変わっても、新自由主義が繰り返し強くなってくる。自己責任社会と言い出す人が現れて人気を得るんです。これに対抗するには、保守リベラルと社民を両方合わせなければならない。ですから、僕は、保守を語りながら、「週刊金曜日」の編集委員をやったり、ビッグイシューをやったりしています。
―3年前に、ホームレスの人々が販売する雑誌ビッグイシューを札幌ではじめられました。
どうしたらホームレスの人々が社会との関係性をもてるかが課題でした。
生活保護でアパート暮らしをはじめても、ハローワークとの往復だけになり、部屋ではテレビを見て過ごす。こうした孤独が辛くて、再路上してしまう。こうした人々が社会包摂されて、あわよくば雇用される。その一番いい突破口が「ビッグイシュー」でした。
―大阪出身の中島さんは、子どものころから、公園でホームレスの人々と接する機会があったそうですが、札幌での感触は?
「えっ、ホームレスの人がいるの?」という人が非常に多かった。200人強は存在する路上生活者が見えなかったのです。理由は、排除されないようにそれらしくない格好をしているから。そして、支援物資がある程度ゆきわたる規模だから。それで、「ホームレスの人はいない」と理解され、声にならなかった。
ですから、まずはホームレスを可視化することが重要だと思いました。ホームレスや貧困問題を自覚してもらい、共感を生み出し、社会的包摂を作り出していく。その仕掛けとして「ビッグイシュー」を活用しました。
―札幌でのビッグイシューの効果は?
開始当時、札幌でのビッグイシューの認知度はほぼゼロでしたが、40%ほどに上昇しました。ちょっとした優しさで一歩踏み込み、ビッグイシューを一度購入したことのある人は、彼らを排除する立場にならないと思います。あれを買うのって、まあまあ勇気がいるじゃないですか。ビッグイシューは、そういう自己人格も生み出す装置になっています。
―ビッグイシューが軌道に乗り、最近は商店街の活性化に取り組んでいらっしゃいますが。
生き方を強くしていく、そのための居場所作り。そのケースのひとつが、発寒商店街の「カフェ・ハチャム」です。
ここを通ると、○○さんがいる。そういう空間。過剰にコミットしなくても、「最近寒いね」「雪かき大丈夫?」でいいんです。
商店街は、単に買い物をするだけではなく、「○○さん元気?」ってちょっと声かける長い縁側なんですよね。
それから、若い人が入りやすいよう意識しました。区民会館のような既存の場は、すごくハードルが高い。普通の人たち、市民運動や右翼運動の担い手ではない人たちが生きにくい社会なので、そこにどう仕掛けていくか。それがカフェにこだわった理由です。
コーヒーを飲んで様子を見るだけ、何もしゃべらず帰ってもいい場所にしよう、と。
有料にしたのも、「金払ってコーヒー飲みに来ているんだ」という顔ができるから。そうすれば来やすいんです。
それでいて、毎週土曜に開催するイベントは、オタクっぽい内容も加えています。自分が引っかかるときには来たらいいように。
地域のお年寄りから若い人まで、立ち寄りやすい場を作りたかったのです。
若者の間では、ジモトという新しいムーブメントが起きています。「木更津キャッツアイ」などのドラマが高視聴率をとり、社会とかかわり合いながら生きていく話への共感度がすごく高いんです。
僕が授業で、「ビッグイシューを一緒にやろう」というより、「カフェを作ろう」のほうが、10倍ぐらい反応がいい。「若者はこれから商店街に来るな」という実感がありますね。
―とはいえ、商店街の衰退はひどい……。
もう壊滅状態。これだけシャッター街になっているにもかかわらず、安く貸さない地権者にも問題があります。一軒下げたら値下げ運動が起きる、という話になっちゃう。全国的に同様な問題が起きています。
今計画しているのは、シャッターがおりた店舗を借り、開業したい人に活用してもらうチャレンジショップです。顧客がついて商売が波に乗ってきたら、商店街で出店する。それを条件に、家賃を一定期間免除し、商店街が後押しします。そういうのをやれたらな、と考えています。
―設計主義的な都市計画について批判されていましたが、札幌、北海道の都市計画は?
住みながらみんなでカスタマイズすればいい、と思います。でもね、発寒商店街がダメになった一番の原因は、道路計画なんですよ。JR線にそって道路が造られ、商店街がブツブツ分断されてしまった。発寒中央駅からこのカフェまでに、大通りを2つ横断しなければなりません。こういう都市計画は街を歩きにくくさせるので、考え直したほうがいい。
これから目指すのは、脱車社会のコンパクトシティ。東京などでは、商店街が活気づいています。郊外型の大型店モデルの時代は終わり、中心街へ向かう人が増えている。これが、現在の日本の傾向です。
札幌市も、人が歩いて行動できる範囲を都市計画に取り入れていくといい。そうすれば、僕たちがもう一度、街の中に定着でき、生きられる社会を構築していけるでしょう。
商店街は今、がんばるべきなんですよ。絶対に大丈夫。中心街に人が戻ってきます。
―町おこしは、人材で左右されがちですが。
リーダー不足は感じます。でも、やるのは普通の人でいいんですよ。普通にここに住みながら、社会に疑問を抱いて「何かしないとなぁ」と思っている人たちで。
カフェを始めるとき、最初は大変でした。「どうして、この商店街に自分たちのお金でカフェを作らなければならないのか」って。
まず、金物屋のおじさんをくどいたんです。そして、この建物の大家さんが、自ら店長を引き受けてくださることになって。
ここはもともと喫茶店だったので、改装費がほとんどかからなかったのですが、商店街の人はポテンシャルが高いので、自分たちで直せるんです。換気扇は金物屋さんが、ストーブは燃料屋さんが取り付けました。トイレの改装も全部自分たちでやりましたし。
商店街の人々の眠っていた力が掘り起こされていくんですね。「俺がやってやるよ」みたいな人がたくさんいます。
カフェでのイベントは全て、商店街の人たちが企画しています。みんなの主体性が現れてきて。やればやるほど注目され、売り上げにもつながる。単純に楽しいのだと思います。
―そういえば、中島さんは、「市民」という言葉をほとんど使いませんね。意図的ですか?
僕が対象にしたいのは、特定の問題に取り組む理性的市民ではなく、普通の人たちです。商店街にいる普通のおじいちゃんおばあちゃんたち。普通に暮らす人たちとどうコミュニケートし、そこに通じる言葉を発するか。それが、僕にとって大きな課題です。そこを巻き込んでいかないと、地方分権時代のデモクラシーが成り立たないからです。
―普通の人たちも「市民力」をつけるべきではないでしょうか?
僕は「住民力」と言っているのですが。リーダーの人材育成と同時に、大多数のサイレントマジョリティ、この辺のマンションに住み、地域とかかわっていない人たち、かかわるなんて邪魔くさいと思っている人たちを掘り起こしていく必要があります。みんなが参加しないと、財政的にもこれからの社会はもちません。
北欧型は難しい、と僕は思っているんですね。スウェーデンは、政治に対する信頼度が高く、強烈なナショナリズムが存在します。それを日本に当てはめるのは厳しい。
だから、「中福祉中負担」でいい、と。高齢化社会でそれを実現するには、地域の相互補助で税金を減らす方法、マンパワーによる財政負担の軽減を考えなければなりません。
困っている一人暮らしのお年寄りに対し、税金ではなく、病院に連れて行ったり、買い物を手伝ったり、地域社会で支援する。
国に全部任せないで、住民が近所で助け合う。参加と包摂が一体化した社会、そうした新しいコミュニティを作っていくべきです。
―北海道でそれは実現しそうですか?
北海道は特に、お上がやってくれるという発想が強いですね。北海道での批判は、政府や行政に対する依存の裏返しです。
大阪でもカフェ作りをしましたが、市役所や大阪府庁に頼むという発送はゼロでした。自分たちでどうお金を回すか頭を悩ませて。
でも、北海道では、「行政はお金を出さないのか?」からはじまります。そして、やってくれないと文句を言う。
こうした依存体質は、地方分権時代に最もマイナスに働きます。北海道の自治体は真っ先につぶれていきますよ。現在の地方分権は半分新自由主義で、「地方は自立しなさい」「失敗しても国は知りませんよ」と突き放した態度ですから。
官と民が協働するのはいいのですが、主導するのはやはり住民です。自分たちがどういう社会にしたいのか、そのとき自分たちはどうやっていけるのか。住民たちがプロジェクトを提案し、政府あるいは行政が支援する。その形が一番いいし、そういう社会に変わってほしいです。そのためには、「住民力」をつけ、社会参加していかなければなりません。
―この体質を転換するためのアドバイスは?
いろいろな人を巻き込んでいくっていうのかな。参加したら楽しいよ、という場所をいっぱい作る。このカフェのように、「楽しいじゃん」というのを全面的に出して、どんどん見せていく。「北海道の人は何もしない!」とお説教してもうまくいきません。まあ、行政側にはお説教でもいいと思うんですけど…。
住民には、やったら楽しいよ、という方法で僕はインクルージョンしていきたいですね。
―使い古された「開拓精神」や「ボーイズ・ビー・アンビシャス」に代わる、北海道らしい新たなコンセプトを提言するとしたら?
北海道の最大の長所は、よそ者に対してものすごく寛容な点です。僕は北海道に暮らしてまだ3年ちょっとなのですが、こんなにコミュニティのなかに入れてもらって、主導して動くことができる。こういうのって、他の地方では成り立ちにくいと思います。
それから、大学の人間と社会が近く、お互い気軽にかかわることができるのもメリットです。札幌における北海道大学って、社会との関係性がすごく近いんですよ。大学のあり方として、それは望ましいし、もっと関わりあえばいいですね。
寛容と多様性。許容できる範疇の広さと、懐の深さがある社会。北海道はそれを生かすべきです。