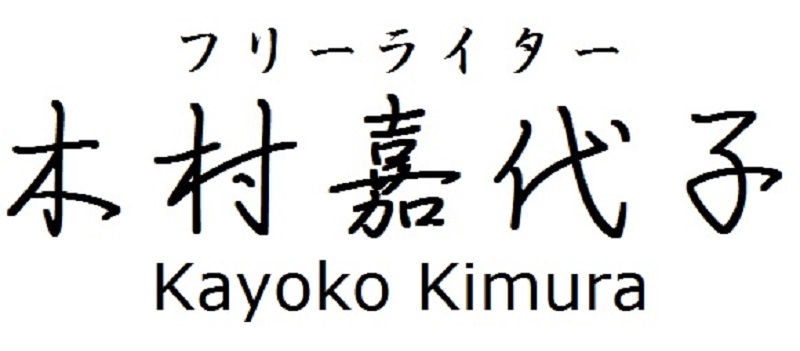今日7月3日(木)午後3時より、東京地裁103号大法廷で、函館市が提訴した大間原発建設差し止め訴訟の第1回口頭弁論が行われました。
傍聴には200人以上が集まり、100人の傍聴席はすべてうまったそうです。
傍聴できなかったのですが、弁護団の報告によると、工藤函館市長は、35分間びっちり、意見陳述を読み上げたといいます。
工藤函館市長の意見陳述は、函館市のホームページにアップされるとのとですが、結びを一部ご紹介します。
(訴訟にいたった経緯に関しては、函館市のHP大間原発の建設凍結のための提訴についてをご参考に)

原発の安全の確保や万一の事故が起きた場合に、誰が責任を持ってあたるのか。政府なのか、原子力規制員会なのか、事業者なのか、その根本のところが極めて曖昧なまま、原発の建設が進められています。
電源開発株式会社という営利を追求する一民間企業の事業のために、27万人の人口を擁する函館市の存立そのものが、同意もなく危機に晒され、そこに住む市民の生命と平穏な生活、そして貴重な財産が、一方的に奪われかねない、そんなことがこの民主主義国家において、許されるのでしょうか。
福島の原発事故によって、はっきり分かったことは、ひとたび原発の過酷事故が起きると、地方自治体、その地域が事実上半永久的に消え去る事態に陥るということです。地方自治体の存立そのものが将来に亘って奪われる、このようなことは原発事故以外にはありません。
戦争もまちに壊滅的な打撃を与えますが、復興は可能です。ある意味で人間はそれを繰り返してきました。戦争による最大の悲劇ともいうべき原爆投下を乗り越えてきた広島・長崎も再生しました。
しかし、放射能というどうしようもない代物をまき散らす原発の過酷事故は、これまでの歴史にはない壊滅的な状況を半永久的に周辺自治体や住民に与えるのです。チェルノブイリや広島がそれを証明しています。函館がその危機に直面しています。電気をおこす一手段にすぎない原発によって、まちの存立そのものが脅かされることになります。
私たち函館市民は、承諾もなく近隣に原発を建設され、いざというときに避難もままならない状況の中に置かれることになります。自分たちのまちの存続と生命を守るために、この訴訟を起こしたのです。それ以外に残された道はなかったということを是非ご理解いただきたいと思います。