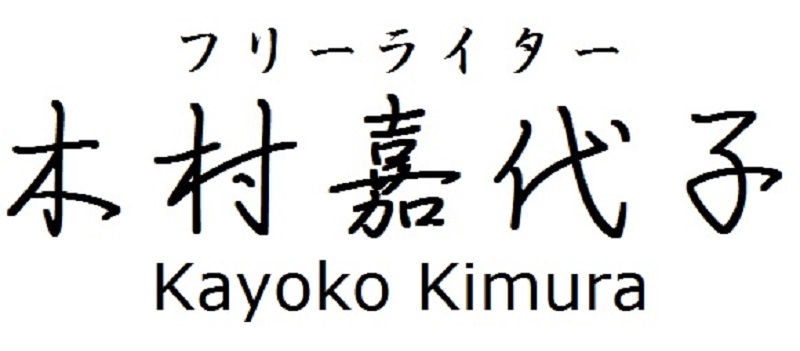『VISA』1994年9月号に掲載された記事です。

英国人ほどパブ好きの国民はいまい。ロンドンだけでも実に8000軒以上のパブがある。彼らにとってパブは、酒を飲む場であり、また社交場である。仕事帰り、夕飯の後、彼らはグラスを片手にいつ尽きるともしれない談笑に興じる。
パブの総称は「パブリック・ハウス」。その起源については定かではないが、すでに12世紀にはパブらしきものが存在すていたようだ。その昔は、宿泊施設をもつイン、食事を提供するタヴァン、おもに酒を供するエールハウスと宿泊兼レストラン兼酒場があった。やがてインはホテルに、タヴァンはレストランに、エールハウスはパブの前身になる。
18世紀に入るとパブは町の寄り合い所的機能をもちはじめ、やがて集会や会議などにも利用されるようになった。そこから上流階級だけの部屋「クラブ」が生まれ、一般人を対象としたスペースが、パブとして残ったといわれている。そして19世紀前後、アルコール好きのウィリアム4世時代、ロンドンを中心にパブは急増を遂げる。現在でも、当時開業したパブが全国に数多く残っている。
イギリスのパブはスタンディング・スタイルである。なかは薄暗く、しかも煙草の煙が充満し、ちょっとヨソ者には近寄りがたい雰囲気がある。だが、数回通い常連客(レギュラー)とみなされれば、これほど居心地の良い空間はないことに気づくだろう。
正直言って、ロンドン周辺のパブはどこかヨソヨソしい。特に女性同士や旅行者が入るにはちょっとした勇気が必要である。それに比べスコットランドのパブは気さくこのうえない。ドアを開けて一歩そこに足を踏み入れれば、こちらが恐縮してしまうほどの歓迎を受ける。

スペイサイドにあるダフタウンは、時計塔のある小さな町。そこに100年ほど前から開業しているコマーシャル・ホテルに併設された、かつての宿屋(イン)を彷彿させる雰囲気のパブがあった。カウンターのまわりにはいくつかの椅子が置かれているだけで、あとは何もない。夜の8時に行っても客すらいない。10時半を過ぎなければ人が集まらないという。
このパブに集う男たちは、ほとんどがウイスキーの製造に携わっている。たとえ違う蒸留所で働いていても、ここではよき仲間だ。自分たちが手がけたウイスキーをチビリチビリやりながら、とりとめのない話に時を忘れる。

同じスペイサイドにあるロイヤル・オーク・インは、地元の男たちばかりでなく、女性のグループや旅行者たちに人気のパブ。バーテンダーのイアンが客の注文に応じ、忙しく立ち回る。口のほうも客との談笑で止まることをしらない。旅行者も例外ではない。地元の人々にとって旅行者はダフタウンという家に招かれた大切なゲストなのだ。だから一度でもともに酒を酌み交わせば、旧知の仲になってしまう。
地元の女性もまた威勢がいい。夫と一緒に、または女性同士でパブに出かけては、ウイスキーやビール片手に世間話に花を咲かせる。ハシゴなども当たり前。
「これからコマーシャル・インに行くのよ」とグラスに残ったウイスキーを一気に飲み干し、勢いよく出ていく女傑もいた。
ちなみにロイヤル・オーク・インのスコッチはシングル1杯が95ペンス(約150円)。人気の銘柄はフェイマス・グラウス。
蒸留所の仕事は朝が早い。“生命の水”を堪能した男たちが、ほろ酔い加減で「お先に」の言葉を残してパブを後にする。
スランジー・バ(乾杯)・パブ!