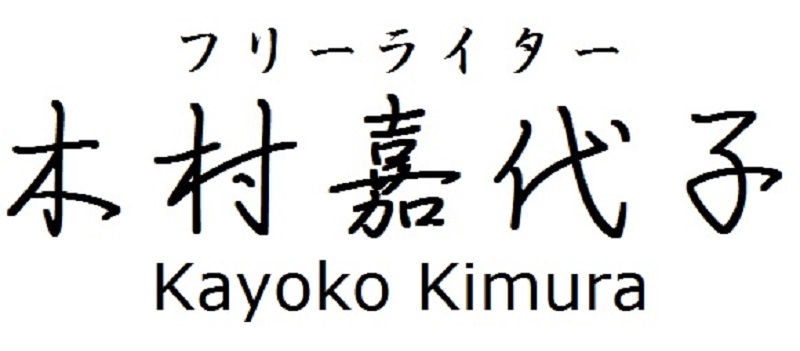『Boulevard』1995年7/8月号に掲載された記事です。
「フルートを習い始めた小学校4年生のとき、札幌でジャン=ピエール・ランバル氏の演奏を聴き、強い印象を受けました。この人と勉強するんだという予感がありましたね。フランスへ行く決心をしたのもこのときだったような気がします。今でも、ランバル氏がファイト満々でステージに登場してきた様子を覚えています。初来日のコンサートで、あのころ彼は42歳ぐらい、今の僕と同じような年齢でした」
クラシック好きの両親に連れられ、当時結成されたばかりの札幌交響楽団の定期演奏会へよくでかけた。フルートを始めたきっかけは、音楽の時間に習うリコーダー。クラスで一番上手だった工藤さんは、いつもお手本に拭いていたそうだ。週に2時間という音楽の時間が一番生き生きしていたという。
「フルートは子ども用がないので、10歳のときはもう大変。管楽器は息を使うので、体力がないとだめです。すぐバテてしまいます。小学生のころの練習時間は30分から1時間ぐらいが限界でした。その後、中学、高校になって上手になろうとやる気が起きてからは、毎日3~4時間は練習しました」
高校まで札幌で暮らし、卒業後、東京の東邦学園大学に入学。しかし、どうしてもフランスへ行きたい、ランバル先生につきたいという気持ちが強く、2年で退学し、パリへ旅立った。その頃は留学が珍しい時代。一度日本を出たらいつ帰るかわからない。非常に勇気がいることだったという。
「フランスにはコネがなかったのですが、札幌でピアノを習っていた先生が留学していたため、その方のお世話になりました。1975年の4月だから、ちょうど20年前のことです。日本の音楽教育はドイツ系教師が多かったため、ドイツに行く人はいましたが、フランスに来る人は少なかったようです。出発の日は、羽田空港に友人が何十人も見送りにきましたよ」
パリの国立音楽院を受けようと思っていたが、自分のレベルがまったくわからない。渡仏した年の夏にランバル氏の講習会を受け、才能を見いだされることに。
「『国立音楽院を受けに来たのか』とランバル先生に直接声をかけられ、学校の試験を受けても大丈夫かなと思いました。フランス語はまったくわからなかったので、日本人学生に通訳をお願いして。日本人の数が少なかったので、パリの音楽学生はみんな知っていました。学生同士の結びつきも強かったですね。パリは、何といっても建物の美しさに感激しました。生活は大変だったけど、毎日のように音楽会に行って…。安い学食もよく利用しましたよ。毎日通うとメニューが飽きてしまうから、いろいろな学食を回ってね。当時、1フランが約80円だったのですが、定食が2フランぐらいでしたからね」
パリに来て4年間学校へ通い、フランスでの生活を続けるかどうか迷いはじめたとき、リール国立管弦楽団に就職が決定する。パリ・エコール・ノルマン卒業の1年前、79年1月のことだ。
「運よくフランスに残ることになりました。日本人でこのオーケストラに採用されたのは初めてということでした。リール国立管弦楽団には8年在籍しました。オーケストラは朝9時から午後5時まで仕事ですから、まるでサラリーマンのような生活でしたね」
その後、ミュンヘンのコンクールやランバン国際フルート・コンクールなど数々のコンクールに入賞し、少しずつソロの仕事が増えていくことに。日本でのコンサート活動も始めた。しかし、86~87年ごろ、オーケストラとソロ活動の両立には限界を感じたという。
「ドイツから夜行で帰ってきてそのまま演奏するというスケジュールで、きつかったですね。オーケストラをやめるということは、定収入を失うことなので、かなり悩みましたけど、パリへ行ってソロになる決心をしました。やはり、仕事がないときは怖いですね。今は2年先までスケジュールが決まっていますが、3年後はわからない。恐怖心はいつもあります。だからこそやりがいがあるともいえますが…」
フルートはいくつになっても、誰にでも始められる楽器。素人が楽しみにやるのにはもってこいだという。ピアノやバイオリンと違い、小さいときから始める必要はない。10歳以下では肉体的に難しいが、反対に、年をとってからも始められる楽器でもあるのだ。現在、定年退職後の趣味として、シルバー世代にフルートが人気上昇中。日本ではフルート教室が増えているそうだ。
「管楽器はソロで活躍するタフな人が少ないのですね。1時間一生懸命吹くと、体中汗だらけになってしまいますから。運動しているのと同じです。逆に、息を使うので、健康的ともいえます。戦後、スイスの療養所では肺結核の患者にフルートをやらせたそうです。よく聞かれるのですが、肺活量はあまり関係ありません。自分で方法を見つけてできるので、誰にでも吹けます。爽快な気分になれるのがいいですね」
もちろん、スランプに陥ることもあるが、あまり気にしない、“楽天的な性格”と自らを分析する。
「フルートという楽器はとても楽天的。フルートをやっている人はみんな明るいですね。不思議なことですが、楽器によって演奏家の性格がずいぶん違いますよ。オーボエ、クラリネットはどちらかというと暗め、バイオリンはパ~としている。ビオラは思考が複雑な人、チェロは自分を表面に出さない縁の下の力持ちタイプが多いですね。フルートは第一バイオリンと同じように、引っ張っていくタイプじゃないとだめ。僕はフルートをやっていて幸せだと思います」
工藤さんがパリに来たころは、学校に日本人が3人ぐらいしかいなかったという。現在、フルート科の教授をしているパリ・エコール・ノルマンには、日本人が約110人在籍している。全生徒数900人のうち300人がフランス人で、その次に多い国籍が日本人だ。
「日本人の演奏技術は優秀です。世界レベルに達しています。観客のレベルも高くなってきましたね。日本では地方に素晴らしいホールがどんどん建ち、オーケストラも増えています。いい環境を作りつつあるように感じます。地方自治体がホールや楽器などハードにお金をつぎ込んでいますが、これからはソフト面を考えなければならないでしょうね。オープンの1年後にホールをカラオケ大会に使ってしまうところもあるのが現実。そうなってしまったら終わりです。日本が、世界的、国内的にクラシック音楽のレベルを向上させていきたいのなら、もう少し考えなければならないと思います」
日本では、クラシックは高いというイメージが抜けない。クラシック音楽のチケットは5000円以上が当たり前で、観客は遠のいてしまいがちだ。
「フランスのコンサートは学生料金などがあるので、100フラン(注:約2000円)ぐらいで一流の演奏家の音楽が聴けるのです。また、日本の場合、外国人なら何でもいいというか、話題になっているものに突っ走って、自分の好きなものを選ぶことが少ないですよね。流行っているのに知らないのは恥ずかしい、という考えがありますが、フランスではまずないですね。自分が好きなものは自分で選びます」
コンサートのプログラム作りから、日本とフランスでは大きな違いがあるという。
「日本では『知らない曲はやらないでほしい』と主催者に言われます。知っている知らないはその人の教養の問題であって、日本人に有名でなくてもいい曲はたくさんあります。バルトーク、ヤナーチェクなど、知っている人は知っていて、聴きたいと思っている人もいるはずなのに、“運命”“未完成”“新世界”みたいなものばかりをやってほしいと。こういう主催者が9割です。地方へ行くと、特にそのようなコンサートばかりになってしまいます。日本の観客も世界レベルに育っていることを、主催者にもっと理解してもらいたいですね。いつもワンパターンのプログラムでは、観客が満足しなくなると思います。演奏家を招待するとき、何をしたいのかをよく話し合うことが大切です」
フランスは、主催者自身が音楽に関する豊富な知識を持っており、経験が豊かなため、さまざまなテーマを作ったり、演奏家のやりたいものをやらせてくれるそうだ。似たようなものばかりになってしまう日本とは違い、内容にバリエーションがあり、偏りがない。フランス人はいつもオリジナリティのあるものを期待している。
「日本とは反対に、フランスでは、『なるべく知らない曲をやってほしい』と言われます。そのほうが観客は喜ぶ。新しい発見、新しい体験をしたいというのです。こうなると、選曲するのが面白いですよ。曲の内容は名前だけで決まるのではないのですから」
音楽の時間に聞いたものがクラシック音楽、という固定観念を持つ日本人は多い。海外から舞台装置やスタッフなど総勢600人を呼び寄せる引越し公演も日本ならではのこと。6万円ほどの一番高い席から売れてしまうのが、最近の傾向だ。海外へ行くよりもいい、というクラシックファンの気持ちもわかるが、そのコンサートへ行かないと一生損したと誤解し、良い悪いの判断もなくでかける人がいるのは残念だという。
「これから先は、そんな悠長なことも言っていられないでしょう。何を成熟させていくか、まじめに考えてほしいですね」
パリで年2回、日本で40回ほどコンサート活動を行い、あとはヨーロッパ、南アフリカ、南米、韓国、シンガポール、ニュージーランドなど各国を回る忙しいスケジュールをこなす工藤さん。観客の反応はそれぞれの国によって違うという。
「ただ、音楽は世界共通の言語といわれるように、モーツァルトのかわいいメロディーはどこで聴いても同じようにかわいいのです。観客の聴くときのエネルギーは、どこもあまり変わらないような気がしますね。演奏中は、演奏家と観客がコンタクトを取り合っている。その会場でコミュニケーションしているのです。それがやりやすい国とやりにくい国はありますが…。観客が一生懸命聴いてくれるときは、演奏家も一生懸命になります。直接会話できなくても、音楽を通して語り合っているのですから。音楽家冥利に尽きると感じるのは、この瞬間です」