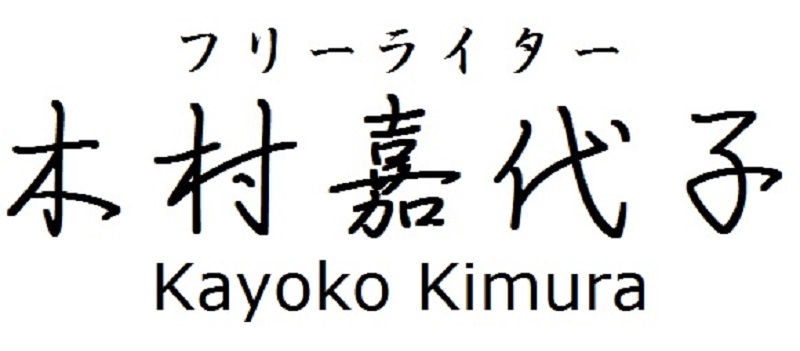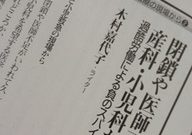『月刊自治研』2014年5月号に掲載された記事です。
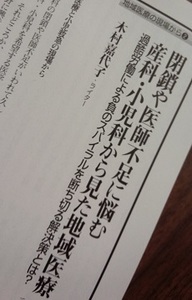
過酷労働による負のスパイラルを断ち切る解決策とは?
周産期医療と小児救急の現場から
産科・小児科の閉鎖や医師不足がいわれて久しい。しかし、実のところ、産科・小児科を希望する医学生や研修医が減っているわけではない。それどころか、女性が医学生の半分を占める昨今、この分野に興味を持つ研修医は相当数いるという。
にもかかわらず、状況が改善しないのには、過酷な勤務体制が影響している。厚生労働省は、診察報酬の改定や産科医療補償制度などの施策を打ち出したが、産科医・小児科医の減少に歯止めはかかっていない。
産科・小児科が直面している課題とは何か? 今回、名古屋市立西部医療センターを訪ね、三〇年以上にわたり小児科として、特に周産期の新生児を担当している鈴木悟副院長にお話をうかがった。
名古屋市立西部医療センターは、市立の城北病院と城西病院が統廃合し、三年前にオープンした。病床数は五〇〇床で、名古屋市北部と西部、隣接する清須市、北名古屋市、春日井市をカバーする。地域の開業医と連携を図り、病診連帯システムを構築。患者がアクセスしやすい医療機関を目指し、医師を集めた勉強会や、市民向けの公開講座も開催している。
ここは愛知県の地域周産期母子医療センターに指定されており、小児医療センター、周産期医療センターを中心に救急や高度専門医療を行う。
名古屋市には一〇〇〇床以上の病院があるなか、当医療センターは産科の年間出産数一四〇〇を誇る。産科病棟は四五床で、看護師は全員助産師の資格所有者。一〇人程度の産科医では手が回らないため、ローリスクのお産は助産師だけで対応し、二四時間いつでも出産できる体制を整える。WHO・ユニセフの「赤ちゃんにやさしい病院」の認定も受けている。
「妊娠、分娩、新生児の成長と、周産期は母子が劇的な変化をする時期であり、生命の誕生にたずさわる仕事という意味で、産科・小児科は医学生や研修医に人気があります。でも、実際に産科・小児科になかなか入ってきませんね」 鈴木副院長はそう切り出した。
現在の臨床研修システムでは、大学医学部を卒業後、二年間の初期研修で、内科、外科、小児科、産科などを回る。産科や小児科を希望していた研修医は、厳しい現場を目の当たりにし、二の足を踏むのだという。そして、三年目のシニアで自分の専攻を決めるときに、別の科を選んでしまうのだ。
当直が多くてオンオフの区別がない仕事
鈴木副院長も「他の科に比べるときつい労働」と認める産科・小児科の勤務。その実態はどうなっているのか?
当医療センターの小児科医はたとえば、次のような日課をこなしている。朝八時半ごろまでに出勤し、入院患者のチェックや採血を行い、九時から外来がはじまる。病棟の回診を昼ごろまでに終えたら食事休憩だが、とれない日もある。昼からは午後診で自分の専門外来をこなし、その間、午前中にでてきた検査結果をチェックするなどして、夕方までにその日やるべき業務をすべてやり終える。
このルーティーンワークに産科・小児科ならではの特殊性が加わる。そのひとつは「オンとオフがはっきりしていない」こと。
赤ちゃんはいつ生まれるかわからない。夕方定時まで仕事をし、帰宅しようとしたときに、早産で未熟児が生まれることもある。そうすると、そこからまた仕事がはじまり、夜中までかかりきりになってしまう。
産科・小児科が敬遠されるもうひとつの理由は、夜間勤務が多い点。「不思議なのですが、子どもは夜に熱を出します。昼間元気に遊んでいたのに、夕ご飯を全然食べないから熱を測ったら三九度あり、お母さんがびっくりして病院に駆け込む。そのパターンが多いのです」
小児救急の場合、内科や外科に比べて夜間の受診患者数が多い。内訳をみると、内科や外科の夜間外来の七~八割が入院するのにひきかえ、小児科の重症患者は二割に満たない。「熱を出しただけで、心配でやって来る。軽症なのですが、数だけは多いですね」
それにともない当然、当直の回数が増える。毎月の当直日数は、小児科医で五回ほど、産科医は月に七、八回。一方、内科は二、三回程度だ。
「病院の当直というのは、みなさんなかなか理解してもらえないのですが、寝ていて何かあったら起きるのではなく、むしろほとんど働きづくめで、患者さんが途切れたら仮眠できる、というのが現状なんですよ。夜間業務というか」
しかも、一回の当直料はどの科も同じ。「比較的ゆっくり寝ていられる科と、ずっと働きつづけなければならない科があっても、金額に差をつけられないのです。本来なら、労働力に見合った当直料が出てもいいのですが…」 こうした賃金体系もまた、医師の現場離れを引き起こす要因になっているという。
当直では、病棟業務と並行して、外来の救急患者を診る。さらに、一〇〇〇gの赤ちゃんが生まれる事態になると、それにつきっきりになり、朝まで休めない。
長時間労働の現実を知り研修生が進路変更
当直が明けてもすぐには帰ることができない。午前中は入院患者の回診、昼からは、内分泌やアレルギーなど自分の専門外来を行う午後診が待ち受けている。つまり、当直の日は朝まで二四時間働き、さらに一日働くため、三六時間勤務になってしまうことがある。
それでも、鈴木副院長が医師になったころと比較したら、労働環境そのものは良くなっているという。「昔は当直が七、八回で、当直明けは完全に帰ってはダメでしたからね。城北病院は小児科医が四人ぐらいでしたので。二日間徹夜したこともあります」
もちろん、「昔はもっとやっていた」など、今の若い医師に通用しない。研修医たちは労働基準法で守られており、意識も変わった。「以前は、『これからこういう患者さんが来るから、症状を勉強してから帰りなさい』と後輩医師たちを引き留めることができたのですが、もう言えないですよ。研修医のほうから、『残ってもいいですか?』と聞かれるならまだしも、上からの権力で残業させることはできません」
最初のうちは「産科や小児科やってみたい」と思っていた医学生や研修医も、研修期間中のこうした過酷な勤務を通して、「これほど忙しいのであれば…」と考え直してしまうのだ。
「大変やりがいがある職場ですが、結局、もっと負担が軽い科に変えてしまうのです。内科はもともと志望者が多いのですが、最近の傾向としては、耳鼻科や眼科、皮膚科といった、日中だけ働いて、あとは自分の時間を過ごすことができる科を選ぶようです」
産科も同様だ。「お母さんがいつ産気づくかわからないので、二四時間体制でなければならず、病院に泊まらざるをえないのです」
研修医が避ける理由を産科に限定すると、訴訟が多いことがあげられる。お産は本来なら九割は元気で生まれる。昔はお産婆さんがいれば、医者の関与なしでお産ができた。そのため、「元気で生まれて当たり前」という意識がいまだに強い。
「でも、運悪く、一〇人のうち一人は難産になってしまうんですね。それが原因で、たとえば障害が残ってしまったとき、『医者の対応が悪かったのではないか』と訴えられるケースがけっこうありますね」
そこで、産科医療補償制度が施行され、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族に、総額三〇〇〇万円の補償金が支払われることになった。
「この制度ができたおかげで、今後はある程度、産科医を守ることができます。産科医が増えてくるのではないか、と期待しているのですが」
産科・小児科を維持するのが公立病院の使命
小児科のもうひとつの課題は、経営効率の悪さだ。「採血の際、大人であれば医師ひとりでできますが、子どもは喜んで手を差し出さず、暴れます。最低でも、医師の他に看護師二人が必要です。子どもには高額の検査もできません。一歳時の体重は一〇キロほどなので、薬も普通の大人の四分の一ぐらいしか出せないわけです」
労力のわりには、収入が少なく、人件費ばかりかかってしまう。小児科が病院の不採算部門といわれるのは、こうした所以からだ。「病院としては、内科医を増やしたほうが儲かるんですね。公立病院であっても経営についていわれますので」
「小児科の切り捨て」を防ぐ目的で、二〇一〇年の診療報酬改定の際、周産期関係の加算点数が手厚くなった。小児入院医療にも点数が新設された。
産科・小児科の存続、医師の増加を促すテコ入れは進められてはいるのだが、現時点ではその効果は表れていない。
「厚生労働省のこうした取り組みが実践できるのは、恵まれている病院だけ。小児科医がいないとできないですし、現場との乖離があると思いますね」
産科・小児科の閉鎖は後を絶たず、その結果、患者の集中により小児科がある病院はますます疲弊する。
「多少財政的に苦しくても、小児科を維持していくのが公立病院の使命でもある、と思いますね。名古屋市の市民である子どもが安全に暮らし、医療を受けることができるように、補助として税金を使わせていただく。それが可能なのは公立病院ですから」
とはいえ、経営不振の公立病院のなかにも、小児科が廃止に追い込まれるのは珍しくない。自治体の財政難で、公立病院に税金を十分投入できないのだ。
「そうなったとき、一番困るのは、小児を持つ親御さんなんですね。そこで、親の会を立ち上げ、『自分の自治体の小児科や小児科医を守ろう』と活動している地域もあります。『小児科医のためにコンビニ受診をやめよう』と呼びかけて」
コンビニ受診とは、コンビニ感覚の夜間受診のことで、小児科医らを疲弊させている原因のひとつになっている。医療費は名古屋市の場合、中学三年まで無料のため、夜間は診療費がかかっても非常に安い。そこで、「日中に病院で二時間待たされて薬をもらうよりも、夜中にいきなり診てもらったほうが便利」と考える親が増えているのだ。夜中に受診に来て、「明日、遊園地に行きたいから、今夜薬がほしい。薬を出すのは当然、それが病院の使命でしょ」と主張する若い親がいるという。
産科・小児科の問題は、医療の現場や政策の面だけでなく、人々のモラルの低下も少なからず関係していそうだ。
仕事と育児を両立できる環境づくりが急務
産科・小児科は女性が比較的なじみやすい分野ということもあり、女医の割合が高い。そこで、仕事と育児の両立が重要な課題となっている。当医療センターの小児科医も、一四人のうち男性は五人だけだ。
当医療センターでは、勤務時間をなるべく厳守するよう、医師たちに呼びかけている。
「家庭を持って子育てしながら働いている女医もたくさんいますから。自分が当直の日はしかたがないにしても、それ以外の日は、夕方の五時一五分過ぎたら、残ってやらなくてはならない仕事があっても当直医に頼んで、できるだけ帰るようにしてもらいます。当直ときは実家の母親や夫に子どもの世話を頼んでも、普段は夕方帰って、家事ができるように」
だた、そうしたシフトを組めるのは、医師の数がある程度そろっているからこそ。この規模の病院で小児科医一四人は多いほうだが、未熟児を扱う周産期医療と小児科救急医療をこなすには、これだけの人数が求められるという。
「労働環境が改善されれば、医師はどんどん増えてくると思うのですが…」と鈴木副院長は言うが、悪循環を断ち切る手立てはいまのところなさそうだ。過重労働を軽減するには、医師の増員を急がれる。
産科・小児科は特殊な分野で、何か仕掛けなければ人材が集まらない。西部医療センターでは、ホームページで病院を紹介したり、研修医たちに「忙しい職場だけど、楽しくてやりがいのある」ことをアピールし、医師の確保に努めている。
医師の偏在が是正されないのには、医局の脆弱化も関係しているという。「医局制度がしっかり機能していたころは、『人手が足りないのなら、誰か派遣しましょう』と、大学の医局から負担の重い病院に医師を送っていただいたのですが、新しい研修医システムがはじまって以降、医局に入る人が少なくなり、忙しい病院に人を送るのが難しくなってしまいました」
若い医師が入ってこなければ、いつまでたっても上の世代が踏ん張ってがんばるしかない。そうした医師たちももはや限界にきており、事態は深刻だ。
「〝辛い仕事〟というのが先に立ち、進みたい分野に進めない。産科・小児科をやりたがっている医師を支えていくのが一番幸せなのに、もったいない話ですね」
産科・小児科が抱える難題の解決には、いまだ特効薬が見つかっていない。