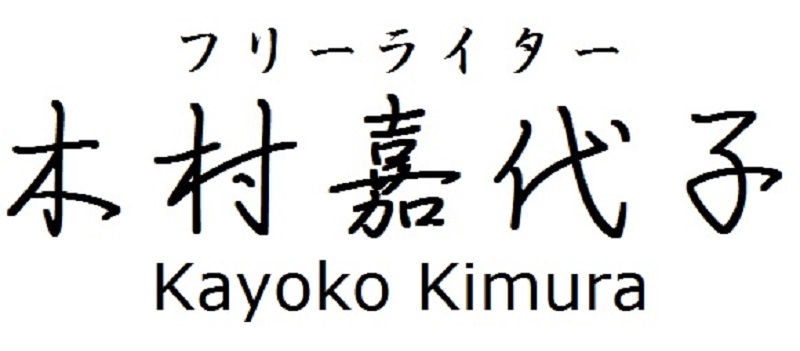『週刊女性』2014年7月22日号に掲載された記事です。

「母が09年、父が11年に亡くなったんですよ。短期間に2人分のお葬式やその後の手続きをしたら、死がリアルになるじゃないですか。それからいろいろ調べ始めているんです」
Kさん(47歳・主婦)は終活を開始したきっかけをそう語る。両親のお葬式を出すまでは、まったく意識になかったという。
夫はひと回り上の60歳。子どもはいない。普通に考えて、おひとりさま予備軍だ。母は66歳で他界、父は60歳のとき脳梗塞で倒れた。最期が「すごく先ではないかも」との自覚もある。
両親の葬儀は、実家の福島県で互助会に頼んだ。祖母の時代からの知り合いで、違和感はなかった。親の後始末をきょうだいで引き受けながら“いま、私がやっている役は誰がやるの?”と、はたと危機感を抱いた。
「子どもがいれば片付けてくれるのでしょうが“ホント、どうするの?”って」
妹や弟は健在だが、このご時世、先のことはわからない。その意味では、子どもがいても状況はさほど変わらないのかもしれない。
たまたまテレビで“介護難民”の番組を観て、ひとり暮らしの低所得者の後始末は行政がすると知った。福祉課の職員が火葬に立ち会い、無縁仏に葬られるのを目にし「これしかないの?」と茫然……。
「番組で見たようになりたくないと強く感じました。何も考えないで死を迎えたら、自分がいいと思わない、よりイヤなほうの終末になってしまいそう。楽しく自分らしくできるなら絶対そっちにしたい。いま始めれば可能かもしれないので」
だが、書類の提出や葬式、納骨などを誰に頼むかといった、最も気がかりな〝おひとりさまの終活情報〟がなかなか見つからない。ネットで探すにも、キーワードが思い浮かばないのだ。
あちこちにアンテナを張っていたところ、冠婚葬祭のサポートをするウェルライフ主催の『これから楽交』を友だちに紹介され、5月から講座や入棺体験などに参加しだした。入棺した感想は「狭いんだな。目を開けても暗いと聞いてたけど、あーホントだ」とまだ現実味がない。参加者の意見はさまざま。自分と違う感想を聞くのがおもしろかった。
「終活は、果てるときを把握して、いまをよりよく生きる。そんな感覚なのかな」
そう語るKさんは最近、最期から逆算して、老後の費用を計算してみた。
「年金の足りない分を貯金しなければならない、と言われて。会社勤めが長かったのですが、金額を出したら“わー、大変!”って。厳しい世の中だなぁ、と」
ひと口に終活といっても介護、お葬式、お墓など、その範囲は驚くほど広い。Kさんがまず取り組もうとしているのは、お墓。結婚直後に夫から建てるつもりと聞いたが、いまだにそのままだ。
「骨が土に還って木の栄養になり、次の世代が木や花を見て“きれい”と思ってくれたらうれしいかな」と、目下のところ、樹木葬に注目しているという。
Sさん(57歳・NPO職員)は23年前、34歳のときに散骨を決めた。NPO法人『葬送の自由をすすめる会』(東京)を仕事で知り、すぐに登録したそうだ。
「もう子どもは作らないと決断したときに“私にはお墓がない、じゃあ散骨しよう”と思ったんですよね」
子どもがほしくて、33歳で「めちゃくちゃお見合いをした」。高齢出産のリスクも考慮したら、35歳までに出産するのが理想。しかし、仕事が充実していた時期で結局、結婚に踏み切ることができなかった。
「父の墓は弟が継ぐわけでしょ。家族はそういうもの、と育ってきたんです。こういう家族意識を持っているから、枠からはずれた状況にどう対応するか、いつも考えなければならない。長男に嫁いでいたら、終活は考えなかったと思います」
今までの日本人は終活など必要なかった。結婚して、子どもができて……と社会が定めるレールに沿って生きていれば、行く末が決まっていたからだ。しかし、そのシステムが崩れ、人の生き方は多様になった。
「ひとりだけ放り出されたら、すごく不安。だから“どうしよう、何かしておかなくちゃ”と思ったんです」
50代になり「その前に老後があるんだ」と気づいた。
父親が死去し、15年前に母親が脳梗塞で倒れたときにマンションを購入。母を抱え、実家の一軒家に住むのは困難だったからだ。
「当時は自分の介護や老後はまったく頭になく、マンションが終の棲家と思ったの。コミュニティーがあって、お祭りも多い下町で、楽しく生きるのが私の老後だと信じてたのね」
ところが、母親の介護を通して「ここで死ぬのは無理だ」とわかった。
「最初は私がご飯を作っておけば、母は自分で出して食べたの。でも、どんどんダメになるんですよ」
初期のうちは、配膳などの介護サービスを利用してひとりでできるかもしれない。でも、認知症は進行する。それを目の当たりにし、「マンションでひとり暮らしの老後はありえない」と考えるようになった。
「マンションを処分して、貯金を使えば、どこか施設に入ることができるかもしれない。だから自分で判断できる間に後見人を頼むとか、“こうやって片づけてね”とエンディングノートに書いておこう、と」
終活歴の長いSさんは、「その時点でいいと思っても、あとになって役立たないケースがたくさんある」と学んだ。施設に入所している母親のお葬式も、「陽気な母親だから、ワイワイにぎやかに行うつもりだったのですが、母の友人が次々と亡くなって……」と予定通りになりそうにない。Sさんは言う。
「終活は常に更新していかないと」
記者も40なかばで終活をスタートした。そのころ、30代と40代の身内が相次いでガンを告知され、〝死〟が身近だったからだ。
自分の最期が急に心配になった。そして、余命を告げられてから冷静に準備する自信はないと悟った。
「元気なうちにある程度、用意しておこう」と、NPO法人『葬送を考える市民の会』(札幌)の講習を受け、母の着物で死装束を仕立て骨壺を焼いた。
エンディングノートを埋めるには、遺体安置や火葬などの場面を想像しなければならず、かなり覚悟がいった。自分史や連絡先を書きながら、懐かしい人々を思い出し、ウルッときたり。
終活はこれまでの自分を見直す機会になり、「残りの人生を愉快に!」と気持ちを切り替えてくれる。
40代はターニングポイント。終活デビューに早すぎる年齢ではないのだ。