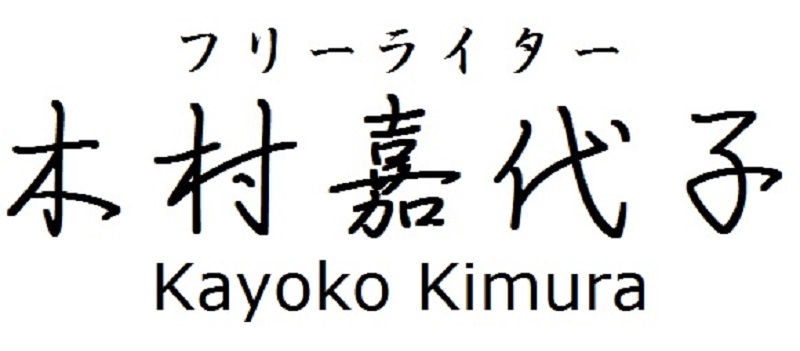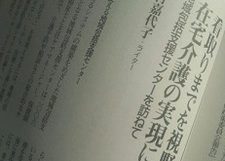『月刊自治研』2014年4月号に掲載された記事です。

愛知県岡崎市・社会福祉法人岡崎市福祉事業団の高年者センター岡崎地域包括支援センターを訪ねて
高齢者を在宅で支えるシステムの構築を目指した地域包括支援システム。その窓口となる地域包括支援センターは二〇〇六年にスタートし、社会福祉士と主任ケアマネージャー、保健師の三職種がチームを組んで、介護予防や相談などの総合的なサービスを行っている。
「療養や介護をなるべく自宅で」を実現させるには、地域の医師のバックアップが欠かせない。しかし、医療と介護との連携にはいまだ課題も多く、地域包括支援システムの謳う「入院、退院、在宅復帰を通じた切れ目ないサービスの提供」も、必ずしも十分とは言えないのが現状だ。
「家族や地域が生活を支える」社会は崩壊しつつある。一人暮らしの高齢者の中には誰も面倒をみてくれず、そこに住んでいることさえ地域に知られていない人も多い。病院で適切な治療を受けたとしても、入院中と同じ生活ができなければ、退院後に悪化し、また病院へ戻ってしまう。その繰り返しを止めるには、薬の飲み方を教えるだけでなく、生活指導が必要だ。
こうした生活支援や予防介護への取り組みを地域に働きかけるのも地域包括支援センターの重要な課題の一つとされる。その人らしい生活を地域で包括的に支えるために、センターの果たすべき役割は大きい。
今回、社会福祉法人岡崎市福祉事業団の高年者センター岡崎地域包括支援センターを訪ね、在宅医療の現状をお聞きした。
岡崎市には、小学校区ごとに一四の地域包括支援センターがあり、そのうちの六センターを岡崎市福祉事業団が運営している。各センターのスタッフは、三職種の三名と常勤職員一~二名。なかでも医療知識をもつ保健師は、在宅介護の現場と医療をつなぐ重要なキーパーソンである。
双方の現場から見えてくる連携の課題とは何か。医療機関への勤務経験を持ち、いまは岡崎市中央地域福祉センター・地域包括支援センターに保健師として勤務する杉浦敦子センター長にお話をうかがった。
医師との人脈作りから調整までを担う保健師
病院の集中治療室の看護師をしていた杉浦さんは、岡崎市が地域包括支援センターを立ち上げたと同時に保健師になった。
「前の職場では『患者が何を言おうと助けなきゃ』だったのですが、一八〇度変わりましたね。『血圧が高いのでお風呂入ってはいけません』から、『本人の楽しみをとってはいけないな』と」
医療は病気を治すのが第一の目的で、治療中はさまざまな制限が強いられる。しかし、在宅医療では「本人らしさ」が尊重されなければならない。在宅で可能な限りその人らしい生活を送るには、医療的判断が不可欠で、保健師が配属された理由もそこにある。対象者をよく理解し、医療現場の常識と生活の場の常識をすり合わせるていくのが、保健師の仕事だ。
杉浦さんも当初、医師の言葉に従い、「あれもダメ、これもダメ」と厳しかったと反省する。そして、その人らしい生活を実現させるために、本人のやりたいことを医師に知らせるのが保健師の役目だと気づいた。「『漬物を食べないように』と医師に言われると、患者は『はい』と従い、楽しみがゼロになってしまう。そこで、『一日一切れぐらいならいいのでは?』と医師と調整するのが保健師なんです」
ただ、保健師になって八年目の今でも、医師にこうした発言をするのは難しいという。
「医師は患者の生活まで見る意識を持つことは難しいと思います」 杉浦さんも、病院にいたときは、患者が退院した先は見えていなかった。「入院中は看護婦が体をふき、薬の管理もし、完璧ですよね。医師も看護師も、退院後は家族が洗濯し、誰かが面倒みるのは当たり前だと思っていました。患者がひとり暮らしかどうか知ろうとしなかったですし」
地域の医師との距離を縮め、人脈を広げるのも、保健師の腕にかかっている。高齢者を支援していくうえで一番困るのは緊急事態の対応だ。かかりつけの医師がいない場合、相談できる医師はなるべくたくさん知っていたほうがいい。
忙しい医師とコミュニケーションをとるために、杉浦さんは工夫を凝らす。「高齢者が通院の際に一緒についていくのも、病院に出向くタイミングのひとつ。家族と医師の言うことが食い違っているときなど、『実際はどうですか?』と医師に聞き、解決していきます」
また、自ら体を張って、医師の開拓をすることも。「自分が風邪を引いたときなど、いろいろ病院を変えて、出かけるようにしています」
こうした苦労の甲斐もあり、センターが立ち上がったころに比べると、往診する医師は増えている。最近では、医師のほうから、「この方、困ってるよ」と情報をもらうこともあるという。
それでも、杉浦さん自身は、「まだ理想通りにはできていない」と痛感している。「往診できる医師や定期的に巡回する薬剤師などを調整するために、日頃から情報を共有すべきなのですが……」
生活支援に欠かせない地域の協力
在宅医療が可能かどうかは、支える地域医療の発達だけでなく、地域のつながりが密か淡白かも関係してくる。岡崎市福祉事業団が担当する市街地はわりと地域のつながりが希薄だ。そのため、地域でできることは地域で見守ってもらう支援体制作りにも力を入れる。
「地域力はそれぞれ違い、『絶対孤立死を出さない』とがんばる地域もあれば、そうでない地域もあります。派閥とか、プライドのぶつかり合いとかも。『地域でどうにかしよう』という気持ちをもってもらうよう心がけています」と杉浦さん。
地域によっては、介護関係者とのかかわりに消極的なところもある。それでも、最近は孤立死がどこでも起きるせいか、以前に比べれば、いずれの地域もオープンになってきた。孤立死など困りごとを相談されたときや、町内会の会長が変わる時期を逃さずに、地域に近づいていく。そのために、地域とのつながりをつねに持ち、アンテナを張っていなければならない。
杉浦さんたちはまめに地域を訪問してはいるが、月に数回、八時~一七時しか観察できない。それ以外の時間は、地域の民生委員や福祉士との協力を呼びかける。
六〇~七〇代はまだ元気な人も多く、家で寝込んでいても、地域の人に気づかれないときもある。そこで、その存在を知ってもらい、電気のチェックなどを依頼し、「最近見かけない」といった情報が入ってくるようにしておくのだ。
民生委員や福祉士との集まりにはなるべく出向き、地域の人々と顔の見える関係作りも怠らない。会合が終わった後に三〇分ほど時間を設け、勉強会などを開く。「こうした会は毎月行います。あれもこれもではボランティアの負担になってしまうので、『何に困っていて、お互いどうしたらいいのか』を話し合い、役割分担を決めていきます」
センターが立ち上がったころは、夜中二時ぐらいに「どうしましょう?」と地域の人から電話かかってきたそうだ。今は「家で大丈夫」「病院につれていこう」と地域で判断できるるようになり、夜間の呼び出しはだいぶ減った。
介護支援において、高齢者の虐待も深刻だ。ひとりで両親をみているケースも多く、一生懸命やればやるほど煮詰まり、虐待につながる。それを避けるために、「どうしたら楽な生活になるか、ストレスを解消できるか」をコーディネートする。
「だからといって、私たちが出すぎるのもダメなんですよね」と杉浦さんは言う。家族や地域の支えがある場合、その家族力や地域力を落としてはいけない。仕事をやめて介護をするのでは負担が大きすぎるので、介護する側の生活スタイルを崩さないよう配慮する。不足している部分を正確に把握し、そこを補ったうえで家族にも関わってもらう。
イベント的アプローチで介護予防を地域へ
地域包括支援センターの取り組みのなかで、あまり進んでいないのが、介護予防の分野だ。介護保険制度は寝たきりになったら使うもの、という意識がまだまだ強く、「こんな状態になるまで…」と驚くのも珍しくない。今後は、地域の医師との協力をもとに、病気や介護にならないための「介護予防」の確立がよりいっそう求められる。
三河地方にはトヨタ自動車工業がある関係で、岡崎市にもある時期、さまざまな産業の従業員が大量に増えた。それが団塊の世代で、そのまま持ち上がって高齢化している。その割合からして病院も介護施設の数も足りず、介護関係者の警戒心は強い。
しかし、施設サービス課・居宅包括支援班の小林節子班長は、「当事者にはさほど危機感がないのでは?」と懸念する。それゆえか、介護の観点で地域に入っていこうとするとガードが堅くなる。「拒否されたら終わりなので、〝元気ハツラツ出張測定〟を紹介し、『健康相談はどうですか?』と、イベント的に地域に少しずつ入り込むようにしています。身近な健康を切り口にしたほうが受け入れられやすいですね」と小林さん。
杉浦さんも、「出張測定で『最近こうなんだよ』と相談され、『病院に行ってみたら?』とアドバイスしたら、結局、病気の発見につながったんです。本人は痛くも痒くもなかったので、異常に気づいてなかったのですが」と話す。そしてこう続ける。「健康でなければ生活は成り立ちません。健康を保つには予防が必要です。病気になったら医師と連携しなければならない。『生活・健康・病気』は横でつながっていると感じています」
さらに、シルバー世代のマンパワーを地域でどう活用するか、それもセンターが考えていかなければならない。「六五歳になったとたん介護になるわけではなく、七〇や七五歳でもまだ働ける、ボランティアができる元気な方がいます。そうした人たちのやりがいや居場所を提供するコーディネートは、包括のこれからの課題ですね」と小林さんは言う。
地域包括支援システムでは、保健師が登場しない場面はない。「保健師として介護現場で働くメリット? 賃金的にはそう言えないですねぇ。福祉の仕事は社会的に地位がなかなか向上しません」と杉浦さんは苦笑する。
医療を基礎資格に持つケアマネージャーの多くが看護現場に戻っている昨今、保健師の仕事量は増えるばかりで追いつかない。医療現場の最前線で働いた保健師は、地域包括支援センターにとって貴重な存在だが、そのような保健師の確保は難しく、全国的に人材不足だという。
看取りまでを視野に入れた在宅介護に向けて
在宅医療の最終段階は、自宅での看取りにある。家で最期を迎えたいという家族は増えているが、現実はなかなか難しい。杉浦さんは、一般的な「孤立死」のとらえられ方について、違和感を抱いているそうだ。「ひとり暮らしの人が家で息を引き取ると、地域の方も、『死なせちゃった』みたいなところがあります。でも、朝行ったら亡くなっていた、というのは、ぎりぎりまで自宅で今まで通りの生活ができていたということで、見え方によっては、すごく幸せなことではないでしょうか?」
病院が遠くて見舞いに来てもらえなかったり、チューブにつながれて病室にいるより、自宅で寝たきりでも、誰かが頻繁に「元気?」と顔を出してくれるほうがいい。そういうひとり暮らしの人もいる。「家で亡くなるのを孤立死にしてしまうと、自宅で看取りができなくなります。すぐに発見されるのであれば、孤立死ではないと思うんです」
本人が希望していても、保健師など医療判断のできる人が近くにいなければ、苦しんで寝ているのを見て病院や施設へ入れてしまう。杉浦さんがかかわったなかでも、自宅で看取ったのは二人ぐらいだという。
看取りまでの在宅医療に発展させるには、地域包括支援センターを中心にした、医師と地域の連携をいっそう強化していく必要がある。
高齢者支援では、介護に関わるさまざまな職種の人たちの情報交換が欠かせない。地域包括支援システムでは、ケアマネージャーや社会福祉士、保健師、医師らが意見を交わす場として、定期的に地域ケア会議を行うことになっている。岡崎市福祉事業団では、各センターが持ち回りで月一回ほど会議を開く。
この会議にも、医師が関心を示すようになった。「会議に出席できないまでも、『こういうことに注意してください』と意見を寄せる医師が増えました。昔はまったくだったのですが」と小林さん。会議内容の幅が広がっているのはセンターが力をつけてきた証、と小林さんは評価する。「『参加してよかった、医療にとってもためになる』と医師に実感をもってもらえるような活発な会議をやっていきたいと思っています」
介護はまったなしの状況にある。制度化しないと、生活を支えることができない時代。それを仕掛けるのが地域包括支援センターだ。これまで培ってきたノウハウを独自の地域包括支援事業に生かし、受け身の姿勢から、積極的な働きかけへ。それが、介護と医療、そして地域との溝を埋める喫緊の課題といえる。