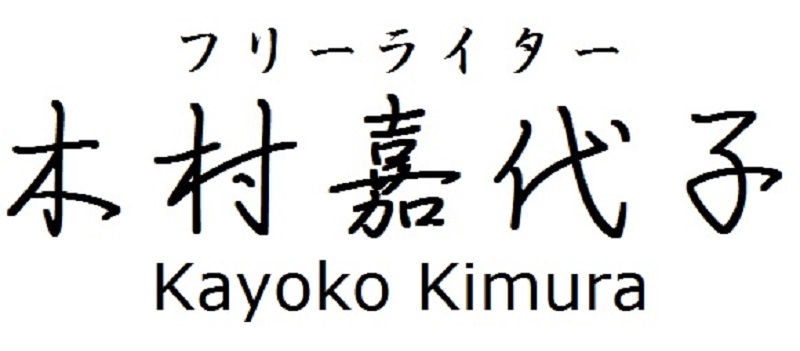『月刊自治研』2014年8月号に掲載された記事です。

質の高い訪問看護システムの構築を
治療とリハビリを提供する訪問看護ステーション
うつ病や認知症などの精神疾患で医療機関にかかっている患者数は年々増加し、二〇〇八年の厚生労働省の調査では、三二三万人にのぼる。精神疾患にはいまだ差別偏見があり、受診しないケースも相当数いると考えられ、実際の患者数はもっと多いと推測できる。
二〇一一年には精神疾患が国民に広くかかわる疾患として、がん、脳卒中、心臓病、糖尿病の「四大疾病」に加わり、「五大疾病」となった。
精神疾患患者が増えている一方、日本の精神科医療体制は不十分で、多くの問題が存在している。
そのひとつが、長期入院の実態だ。日本の平均在日数は約三〇〇日で、一年以上入院している精神障がい者は約二〇万人。他の先進国に比べて群を抜き、「地域で支援」に向かう諸外国の流れに逆行している。
日本の精神科医療の歴史は、一九〇〇年(明治三三年)の私宅監置を中心にした立法制定にはじまり、「精神障がい者は収容する」のが主流だった。戦後、欧米の精神衛生の導入や人権尊重の観点から、精神障がい者のための法律は改正されるが、一九六〇年代に精神科の病床を増やす政策をとり、「入院ありき」の傾向はつづいている。
精神科医療が改善されないのには、入院費の診療報酬が一般病院よりも安く、精神科特例で精神病床の人員配置基準が一般病床より低く設定されているからでもある。少ない人数で精神状態の悪い患者を看るのであれば、隔離拘束は避けられない。
劣悪な精神科医療への批判は高まり、医療費削減に待ったなしの状況も相まって、近年、国は精神障がい者を地域へ戻す方策へと転換した。地域移行に向けた具体的方策を議論してきた厚労省の検討会は、二〇一四年五月二九日に、全国に約三四万床ある精神科病床を大幅に削減する方針を打ち出した。現在入院中の約三二万人の精神疾患患者を地域に帰す計画だ。
しかし、地域の受け皿づくりはまったく追いついておらず、精神障がい者が住み慣れた地域で医療支援を受ける体制を整えるには、数々の難題をクリアしていかなければならない。
精神障がい者を住み慣れた地域で支援
この四月、株式会社八豊会を起業し、訪問看護ステーション「タウンサークル」を立ち上げた八杉基史さんはこう言う。
「日本の医療体系では、健康保険の多くが入院や外来という病院医療に回され、訪問看護や往診・訪問診療などの地域医療の予算は非常に少ない。精神障がい者を地域に帰すのであれば、入院中と変わらない資源を地域医療に投入しなければ……」
作業療法士の八杉さんがこの会社を設立したきっかけは、岡山県唯一の公的精神科病院、岡山県精神科医療センターに勤務していたときに、「退院した患者が、地域で適切な支援を受けているのか」と疑問を持ったからだという。
作業療法士とは、作業を通し、障がい者の残された能力を引き出していくのが仕事。入院中であれば、作業療法士、看護師、ケースワーカー、臨床心理士らがそれぞれの特性を生かしながら、患者の良さを引き出すリハビリができる。しかし、地域に帰った後にこうしたリハビリは継続できない。病院がフォローアップするといっても、患者の生活を全部把握するのは難しい。
「退院後に備えて、食事や掃除、日中の活動などをある程度練習しますが、実際に行われているのだろうか、と。入院中の作業療法が、地域ではたして役に立っているのか。それを検証したかったんです」
医療センターではデイケアを担当し、患者が「どのような日常生活を送り、地域でどのような人間関係を作っているのか」を知るために在宅訪問をしていた。
病院の周辺に約三〇〇人の患者たちがアパートを借りて住んでいる。患者の話を聞いて、「以前暮らしていたところは病院から遠く、通院が大変で交通費がかかる」「田舎に帰っても、いざ対応してくれる人がいない」といった理由から、病院の近くに住みついたというのがわかった。病院側にも、再発防止のためには近くにいてほしいという事情がある。
「はたしてそれでいいのか、と正直思いまして。その人が住んでいた地域に帰るのが普通じゃないかな、と。退院後に患者のところに医療を持っていくことができたら、そこに住めるのではないか。そういう気持ちが強くなったんです」
しかし、精神科訪問作業療法という診療報酬はなく、地域に帰った人に作業療法をする手段はない。可能なのは、訪問看護ステーションを設立し、看護師とともに作業療法士が訪問する方法だった。
作業療法の訪問看護で社会復帰を応援
タウンサークルの主な事業は、訪問看護ステーションと相談支援事業所。訪問看護のスタッフは常勤が看護師三名と作業療法士一名(八杉さん)の計四名で、非常勤の看護師は三名。
以前勤務していた岡山県精神科医療センターの元同僚が一緒に働いている。スタッフはみな精神科病棟での経験が豊富だ。精神障がい者の病状には変化があり、状態が悪くなると対応困難になるが、キャリアを積んだスタッフゆえ、病状悪化のサインを早めにキャッチして適切な措置ができる。
訪問している患者は現在四〇名で、ほとんどが統合失調症。医療センター時代から知っている患者が多い。彼らの住まいは車で五~一〇分程度で行ける範囲内で、一日平均四~五人訪問し、時間は三〇分~一時間程度。回数は週一回から、多い人で週三~四回、退院直後は週五回ぐらいの訪問になる。
相談支援事業は、障害者総合支援法(「障害者自立支援法」より名称変更)に基づいた、知的・身体・精神の障がい者のためのケアマネだ。
主な収入源は診療報酬だが、経営は専門外なので苦労しているという。「経営のための訪問では本来の目的からずれるので、質の高い訪問看護と経営を両立させなければならないのが難しいですね。利潤を上げることで、良い人材を確保し、よりよいサービスを提供できる、と考えているのですが」
就労支援にも取り組み、「一般企業に雇ってもらえるような支援」を目指す。「株式会社にしたのは、他の企業と提携し、能力を備えた人たちに就業の機会を作っていきたいからです。株式会社であれば、就労支援や在宅リハビリなど幅広く事業展開していけますから」
自分の存在を認めてもらえる。それを最も実感できるのが就業活動だ。「福祉的就業であれ、一般企業であれ、自分が役に立っていると感じれば、元気になります。でも、精神障がい者はひとりではなかなかできない。企業からも本人からも喜ばれるような支援をしていきたいですね」
精神障がい者の場合、短期間は勤められても、サポーターがいないと継続が難しい。企業と支援する側が協力し、彼らが働きつづけることのできる環境づくりを見出していく。「こちらがしてあげるばかりではなく、本人の力をフルに発揮してもらわなければならないのですけど。がんばる主体は本人で、その気力を引き出すのが我々の仕事だと思っています」
現在、行政と連携して就業支援をしている。パート勤めをしていた精神障がい者が、薬の服用を中断したのが原因で再発・入院し、会社も首になってしまった。しかし、病院での薬物治療ですみやかに病状は回復。本人は職場への復帰を望み、自分の行為で会社を辞めざるをえなかったのも理解している。そこで、患者の病状を行政に伝え、それを受けて、行政の就労支援担当者が患者に寄り添い、失業保険の手続きをすませ、ハローワークや企業に働きかけているという。
「その人の本当のニーズを把握し、できる範囲での支援を一緒に考える。医療機関から信頼され、いろんな機関から利用してもらえるような訪問看護ステーションになりたいですね」
偏見をなくし社会で支える仕組みが必須
精神疾患の発症は、個人差があるとはいえ、社会環境も大きく影響する。
「彼らとつきあって、生きていくのはしんどいことなんだな、と思います。病気になろうと思ってなったわけではなく、夢がひとつずつ壊れていったんでしょうね。自分で対処できるキャパを越えてもやらなければならない。追い詰められたら、誰でも精神疾患になりますよ」
最近、精神疾患の問題は、医療だけで治す医学モデルから、社会の中で解決する社会学モデルに移行しつつある。従来は医師主導で退院後のケアを組み立てていたが、多様な機関が連携して患者を支えるようになってきた。たとえば、岡山県ではここ一〇年で、行政と障害者福祉サービス、保健所、福祉事務所、就労支援、ヘルパー、弁護士や後見人制度などの司法関係者が連携してケアしようと、ネットワーク会議が盛んになってきている。
また、家族への支援も考慮されるようになった。子どもの病気について理解してもらい、対応の仕方を学ぶ機会を作る病院が増えている。家族への教育は、ひいては患者を支えることになる。在宅訪問でも家族をフォローし、心配事を解決していく。こうした取り組みが今後さらに必要になってくる。
とはいえ、日本の精神科の地域医療はまだまだ未熟で、切れ目のない支援にはほど遠い。病院がどれほど高度医療であっても、地域から見放されると、病状は悪化する。精神障がい者は経済的にも社会的立場でも孤立しがちだ。
「暮らしていくには、医療を受けていなくても、困ることがたくさんあるじゃないですか。我々なら、誰かに聞ける。でも、障がい者はその選択肢を持っていない人が多いんですよ」
コミュニケーションに問題があり、「困っているので支援してほしい」と頼めない人がいる。「助けてください」と言うところから、リハビリで身につけていかなければならない。
基本的金銭感覚も同様だ。生活保護で暮らす精神障がい者が多く、一か月の生活費を早々に使いきり、困窮するケースも珍しくない。
さらに、服薬管理も在宅のなかで支援していく。自分では治ったと思い、薬の服用をやめてしまう人もいるからだ。
「趣味の活動も大切になってきます。日常生活での楽みはあったほうがいい。やりたいけどできない人も、少し背中を押してあげればできる。それも地域の支援だと思うんですね」
支援が行き届かないと、生活が行き詰まり、ストレスがたまって再発する。入退院を繰り返せば、社会的および経済的損失が生じる。そうした状況が引き金になり、事件や事故を起こすと、世間は大騒ぎする。そして残酷にも、精神障がい者は社会から排除される。
「本当はもっと人が関与すべきなんですよ。地域の役割は重要です」と八杉さん。
そこで大きな課題となるのが、精神疾患の地域医療を担う人材不足だ。たとえば、精神科の訪問看護師はまだまだ少ない。大学の看護学部は年に五~六校増えており、看護師不足を解消しようと躍起だが、一校の卒業生から精神科へ就職するのは、たとえば一学年八〇人ほどのなかから一~二人だけだという。現場での実習で興味を持つ看護学生はけっこういるものの、家族のほうに差別偏見があり、親から反対されるケースもある。内科や外科が高額な奨学金を出して看護師確保している現状のなか、精神科への就職にはなかなかいたらない。
「偏見が邪魔して、治療が遅れる」のも日本の精神科医療の特徴だ。どのような病気でも、早期発見早期治療が肝心だが、精神疾患への偏見は根強く、精神科へ行こうとしない。家族も本人も精神科に対して抵抗があるため、未治療期間が非常に長くなってしまう。
「心の不調を感じたら、相談したり、受診できる地域の仕組みがほしいですね。一〇代の若い時期から、眠れない、食欲が落ちた、やる気がなくなったという場合には精神保健相談が身近なところでできるようにすべきです。親も、子どもの心の病について気軽に話ができる。そんな社会を構築していかなければならないと思います」
お互いにお互いを見守るような地域であれば、早期発見早期治療もしやすい。そのためには、疎遠になってしまった地域を見直し、地域単位に精神障がい者を支えていく仕組みが求められる。
「岡山県精神科医療センターの入院患者は、県内各地からやって来ます。つまり、精神科の訪問看護機能は県内に点在するのが望ましく、それをぜひとも実現してみたいです。障がい者は、遠くよりも近くの医療機関に通えたほうがいい。そして、次の受診日までは訪問看護で支援していくのが一番だと思います」
八杉さんは、「病院で、医師、看護師や作業療法士、臨床心理士、ケースワーカーが行っている治療・リハビリを地域でも生かすシステムづくり」をミッションだと考えている。「障がい者になったとたん、多くの人は夢や希望を失ってしまう。そうすると、自分の価値観がぐんと下がり、社会的役割も喪失する。でも、残された能力で新たな作業に関与していくことで、別の役割や社会的地位が生まれてくるのです」
精神障がい者の訪問看護は、孤立化を防ぎ、風穴をあけて社会とのつなげる意味合いも大きい。